文教の広場納入事例
語学学習支援システム WeLL(フルデジタルCALLシステム)納入事例
京都外国語大学・京都外国語短期大学 様
(京都市右京区西院)
高度な複数言語運用能力の育成と、知的好奇心を喚起する授業の構築を目指し、
フルデジタルCALLシステム『WeLL』を導入
〜2005年春にも『WeLL』の増設を予定〜
フルデジタルCALLシステム『WeLL』を導入
〜2005年春にも『WeLL』の増設を予定〜

1947年(昭和22年)に開校し、確かな語学力を身につけた多くの人材を輩出してきた京都外国語大学・京都外国語短期大学様(http://www.kufs.ac.jp)では、外国語学部英米語・イスパニア語・フランス語・ドイツ語・ブラジル ・ポルトガル語・中国語・日本語・イタリア語の8学科、短期大学英語科があり、次の3項目を目標とする外国語教育が行われています。
確かな語学力と専攻語圏の専門的知識を修得する
複数の言語と文化への理解力を養成する
豊かな教養と公正な判断力を身につける
同大学では、外国語教育に不可欠なLLシステムやCALLシステム等の語学学習支援システムを早い段階から導入、活用されていましたが、さらなるレベルアップを目指して、2004年(平成16年)11月、当社開発のフルデジタルCALLシステム『WeLL』を導入されました。
導入の背景
(1) 専攻の外国語習得を強力に支援するシステム
同大学ではWeLL導入以前に、すでに別のCALLシステムを導入し、旧来のLLに代わる拡張性、汎用性を備えたそのシステムは教員に肯定的に迎えられ、高い稼働率を示していました。そこでCALL教室の増室が検討されることになり、システムを活用する教員とそれをサポートするマルチメディア教育研究センターを中心とした、導入機種や教室の設備等を検討するプロジェクト・チームが発足しました。
同大学のCALLシステム導入の基本的ポリシーは、専攻の外国語習得を強力に支援するシステムの構築です。しかし、既存のCALLシステムでは、教養レベルの外国語学習には活用できても、専攻の外国語学習の支援という高度な要求には必ずしも応えられるものではありませんでした。
(2) WeLLの先進性・フレキシビリティに注目
プロジェクト・チームのメンバーは、他大学の導入事例の参観、実際に使用している教員へのインタビュー、学会でのCALL関連の報告の聴取、各社CALLシステムのデモンストレーションへの参加を精力的に行う中で、以下のようなWeLLの先進性、フレキシビリティに注目しました。
1.ビデオ教材や一般的なPC用語学教材など、音声の付いたあらゆる教材で利用可能な話速変換機能(オーディオユニットに搭載)
2.音声教材をサーバー側に一括格納することにより、データ配布の待ち時間が短縮され、送信エラーなどによる授業の中断の危険性を回避できる
3.プロジェクターや学習者モニターに対して個別の映像を表示できる多元送出機能
4.シンプルで優れた操作性
そしてシステム設計の先進性とともに、同大学教員の高度で専門的な要求にも、カスタマイズ対応等によって的確に応える当社開発スタッフの姿勢も、導入決定への大きな要因としていただきました。
同大学では、WeLLの利用によって高度な外国語学習を達成するだけはなく、これにより学生も教員も知的好奇心が喚起されるという新しい授業スタイルを目指しています。


LL教室、CALL教室、新CALL教室(WeLL)の基本的な位置づけ
(1) LL教室
各語学科の専門科目の授業での活用を目的とし、1959年(昭和34年)から導入。同大学における「視聴覚○○語」という名称の科目は、LL教室の使用を前提とした科目として構想されたものです。
(2) CALL教室
従来のLLで行っていた授業を全てカバー。その上でさらに、CALL教室での授業を前提とした、新構想の2言語同時習得を目標とする科目群(「CALL英語−フランス語」「CALL英語−イスパニア語」「CALL英語−ドイツ語」)で使用されています。
(3) 新CALL教室(WeLL)
CALL教室の利用希望が増加しているため、特に2言語同時習得科目群での利用を優先的に割り当て、2005年春にはさらに1教室新CALL(WeLL)教室が増設されました。
なお、2005年度以降、2言語同時習得科目に「CALL英語−中国語」「CALL英語−ポルトガル語」を開講予定です。


WeLLの活用状況

1.WeLLを使った授業
CALL(英語−イスパニア語)、CALL(英語−フランス語)、英語の構造、Extensive Reading、英米語学の基礎、英語の意味と機能、視聴覚イスパニア語、応用イスパニア語、フランス語演習(9科目14コマ)で使用。
2.使われている主な機能
● LL機能=グループレッスンでディスカッションを行ったり、ペアレッスンで会話練習。
● AV機能=教室に設置された2面のスクリーンの活用。2言語同時習得科目の場合、2言語に共通の映画等を流した後、一方のスクリーンに英語のチェックポイントを表示し、もう一方のスクリーンにフランス語のチェックポイントを映し出して、同じ表現を2言語で同時に比較したり、一方で映像を流しながら、もう一方でその映像のスクリプトを提示している。(学習者用PC、学習者間モニター、2台のプロジェクターの合計4つの出力先に、個別の映像教材を送出可能)
● CAI機能=音声ファイルを教材として配布し、学生に繰り返し練習させるだけでなく、スピーキングテストとして学生が録音したファイルを回収するなど、PCベースならではの機能をフル活用している。
3.使われている主な教材、アプリケーションソフト
● アルク=NetAcademy(※)
● ALSI=SMART-HTML(※)
● システムインテグレータ=作って教材(※)
● マイクロソフト=Office Pro 2003
※e-Learningシステムとして学内ネットワークを介して利用
ユニークな4人掛け円卓ブース

2言語同時習得科目群では異なる学科の学生間の授業内でのディスカッションを重視します。そのため円卓ブースによる座席配置となりました。
CALL機能の活用としては、教員−学生というコミュニケーション支援のみならず、学生−学生間のコミュニケーション支援、とくに英語を専攻する学生と、英語以外の言語を専攻する学生など、お互いが異なった言語に触れ、そこで考え、感じたことを即座に話し合い、CALL機能を活用して分析、確認することが、2言語同時習得をより促進するという考えに基づいています。
既存の学内Windows環境と融合

同大学では、既にActive DirectoryベースのWindowsドメイン環境が導入されていました。WeLLシステムに関しても、独立したドメイン/ワークグループ環境を構築するのではなく、既存の学内Windowsドメインに、WeLLのサーバ、コンピュータが参加するという形態で導入されました。
また、2005年春にはシングルサインオン(ユーザー名の入力がWindowsログオンに一本化)に対応予定で、連携・融合度が一層高まり、より使いやすくなります。
小野隆啓 教授のお話
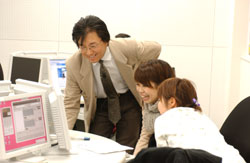
機能面では、CALLシステムとしての基本的な機能は揃っており、教材がデジタル化(ファイル化)され、コンピュータを使っての教材の使用が扱いやすくなっています。ボリューム等が全てデジタルで調整できるため、他の教員が変更しても再起動することでリセットされるので便利です。
操作面では、多様な機能があるにもかかわらず、シンプルな操作画面で視覚的にもわかりやすなっている点が評価できます。
一方、学生の評価ですが、コンピュータの操作に慣れている学生と慣れていない学生との間に差がありますが全般的に好評です。特に話速変換機能が学生の学習への取組み意識の向上に役立っており、既存のCALL教室での授業時より集中して授業に参加しているという傾向があります。
